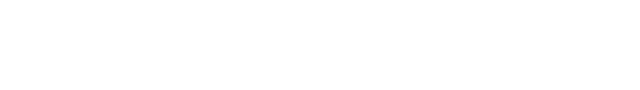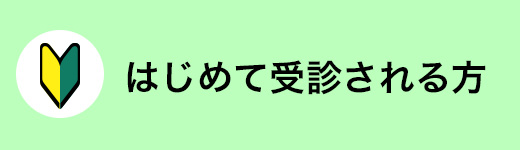性感染症、かゆみ、おりものの異常
性感染症は、今や誰がかかっても不思議ではない感染症となってきました。
ひと昔前までは、私には関係ない! 調べる必要はない! と思われていましたが、近年では10歳代〜60歳代まで見られるようになりました。いつ感染したのか? 誰から感染したのか? など分かりづらくなっているのが事実です。
しかし、いつもと違う、量が多い、かゆみがある、色が違う、匂いがあるなどの場合は受診が必要な場合があります。
クラミジア感染症(クラミジア頸管炎)
クラミジアは性感染症の大多数を占めます。クラミジア・トラコマティスという通常の抗生剤では治りづらい菌が原因です。地域差もありますが、都内でも患者が増加しております。
- 症状:ほぼ無症状です。ごく稀に初期に透明なおりものが増加することがあります。オーラルセックスで咽頭に感染することも多いです。
- 検査・診断:子宮の入り口に細い綿棒を挿入しPCR検査をします。痛みはほぼありません。
- 治療:抗生物質を内服します。
- 治癒判定:3週間後以降に同じ検査を行い、治癒判定を行います。
淋菌感染症
クラミジアの次に多い感染症です。クラミジアと同時感染もしばしば見られます。
- 症状:ほぼ無症状ですが、帯下が黄色くなることがあります。排尿時に痛みを伴う場合もあります(男性は尿道炎で痛みが出やすいです)
- 検査・診断:子宮の入り口に細い綿棒を挿入しPCR検査を行います。痛みはほぼありません。
- 治療:抗生物質の点滴を1回行います。
- 治癒判定:3週間後以降に同じ検査を行い、治癒判定を行います。
カンジダ外陰炎・膣炎
カンジダというカビの一種の菌が増加することで起こります。かゆみがあり白っぽい塊状の帯下が増えます。性行為がなくても発症し、何度も症状を繰り返すことがあります。
妊娠中は膣内の免疫バランスが変わるのでカンジダ膣炎を起こしやすいです。
- 症状:強いかゆみ、ヨーグルト状のおりもの、性交渉時の痛み
- 検査・診断:帯下の培養検査をしますが(細い綿棒で帯下を採取)、視診のみで判断がつくこともあります。
- 治療:抗真菌剤の膣錠を挿入し、クリームを外陰部に塗布します。
- 治癒判定:症状の改善にて治療終了です。
ヘルペス
ヘルペスウィルスに感染することで、外陰部に水泡・潰瘍を形成し強い痛みを伴います。性交渉があった時期から2日〜10日で発症します。
ヘルペスは口の周囲にできることもあります。一度感染してしまうと、ウィルスを完全に排除することは困難となるため、妊娠時や免疫機能低下時に再発することがあります。
-
症状:外陰部の痛みが非常に強いです。排尿困難・歩行困難になることもあります。
発熱したり、脚の付け根のリンパ節が腫れたりすることがあります。 - 検査・診断:綿棒で水泡・潰瘍部分のウィルス検査を行いますが、視診や症状で診断がつくこともあります。
- 治療:抗ウィルス薬の内服を行います。症状が軽度であれば、塗り薬で治療します。
尖圭コンジローマ
ヒトパピローマウィルス(HPV)が原因です。性交渉で感染します。HPVがここ最近、子宮頸がんの原因として知られるようになってきましたが、コンジローマの原因にもなります。
- 症状:膣の中や外陰部にイボのようなものができます。ニワトリのトサカのようにゴツゴツした表面であることが多いです。放置すると、徐々にイボが増加してきます。痛みやかゆみはありません。
- 検査・診断:視診が基本となります。
- 治療:外陰部であれば塗り薬を塗布します。膣内の病変は、イボを摘出・焼灼する処置を行います。
- 治癒判定:イボがなくなることで治療終了です。再発することもあります。
トリコモナス膣炎
トリコモナス原虫による感染が原因です。野外での性交渉時に感染することが多数でしたが、浴槽やタオルを介して感染することもあります。
- 症状:半数は無症状ですが黄色いおりものの増加、悪臭、かゆみ、痛みが出ることもあります。
- 検査・診断:おりものを採取し顕微鏡で原虫がいるか観察、もしくは培養検査を行います。
- 治療:抗生物質の内服と膣錠投与を行います。
梅毒
性交渉により梅毒トレポネーマという菌が皮膚や粘膜から入り込み感染します。近年増加傾向にあり、問題となっています。梅毒は進行すると、全身に広がり生命の危険性が生じます。
-
症状:最初は外陰部・肛門などにしこりができ、リンパ節が腫れますが、症状は一旦消失します。(感染〜3週間前後:1期)
次に発熱や倦怠感が出現し、手のひらや全身に発疹が出現します。(1〜3ヶ月:2期)
ゴム腫と呼ばれるゴムのような腫瘤が皮膚・筋肉・骨に出現します(数年後:3期)
10年以上感染すると、脊髄や脳の麻痺が起き日常生活が困難となることがあります(およそ10年程度:4期) - 検査・診断:採血で梅毒トレポネーマに対する抗体をチェックします。この抗体は感染してから3週間ほどしないと検査で検出されないため、疑わしい場合は、日数をあけて再検査を行うこともあります。
- 治療:A、Bいずれかの治療を選択します。A:ペニシリンの内服を1日3回、4週間行います。B:梅毒専用のペニシリン注射を行います。※いずれもペニシリンという抗生物質です。ペニシリンアレルギーの方は使用できないためご相談ください。
HIV感染症(エイズ)
ヒト免疫不全ウィルス(HIV)が、身体の免疫を守っているリンパ球に感染することで、正常な免疫を維持できなくなり、普段感染しないような病原菌やウィルスに感染しやすい状態となります。感染症以外にも様々な疾患を発症します。
- 症状:感染初期は、風邪のような症状が出ます。
- 検査・診断:血液検査でウィルスに感染しているか抗体のチェックを行います。
- 治療:専門家による病状の進行状態、治療が必要となります。HIVは現在の医療ではウィルスを完全に排除することは困難ですが、お薬を飲み続けることで、限りなくウィルス量を減らし正常な免疫状態を維持することは可能となりました。